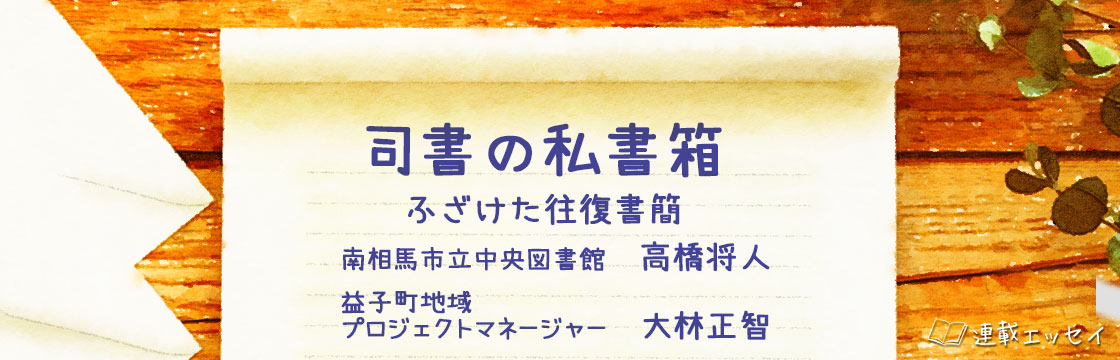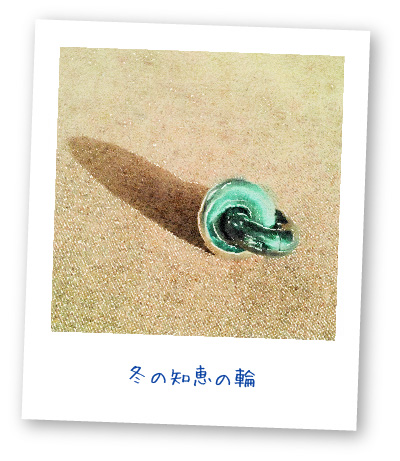(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
No.47「手紙の束と辞書の手紙」
こんにちは。今日は早起きでした。寒暁の張りつめた空気は何とも良いものです。昨夜上げ忘れた自動車のワイパーを見ながら白い息をはきました。
このお手紙のやり取りも、まもなく4年になりますか…。全部で50通弱という数字を見ると少しびっくりします。そんなに話しましたっけ?正月ボケとか曜日感覚不全のような、振り返らずにきた影響の感じがちょっとあります。
「本は瓶詰のメッセージに近い」とのこと。浜に打ち上げられる瓶に入ったメッセージには何が書かれているのでしょうか。SOSなら切羽詰まっていますが、ちょっとした思いが誰かに届いたらいいなと思って流す瓶もあるのでしょう。届いてほしいが半分、届かなくてもいい、が半分。オトナの事情はわかりませんが、この手紙の束を瓶に入れるならそんな気持ちが私の正直なところです。
さて、『司書の私書箱』として手紙を書いてみると、図書館よりも本、読書(本にまつわる体験)のことが多かったなと思いました。まあ、自分の書いた手紙は大林さんに送り付けているので、自分の記憶に残っているところで――というところではあるのですが。
多分、私は図書館員である前に、本を抱えている男なのでしょう。司書として図書館で働けている偶然には感謝しなくてはなりませんね。「私書箱」は己の住所を明らかにしなくても手紙のやり取りができるよねーっていうところから、働いている図書館のことをそんなに出す必要がないかなーなんて思ったのかな。「〇〇の図書館はこんな面で興味深い」「自分の勤務館ではこんな取り組みを!」という手紙よりは…という思いがあった気がします(結局勤務館も書いたし大林さんの仕事の近況にも触れちゃっていましたが)。
今のところ、私の私書箱には大林さんからの手紙しか届いていませんが、アドレスを公開して「ご意見ご感想は司書の私書箱へ」をやったら、どこかから瓶が届くかもしれませんね。面白い。
先のお手紙にあった、辞書で遊ぶ大林さんを想像してちょっと楽しそうだったので、私も昨夜、愛用の『新明解』第四版1にて「熊」を引いて、そのページを見まわしてみました。目に留まったのが、副詞「くねくね」(意味の引用:何か所かで、ゆるやかに曲がりながら、続いていることを表す)。その例文に「太い眉毛を——と歪めて笑う」がありました。この文章は私からは出てこない!と白旗をあげ、そうやって笑うのはどんな状況だろうと考え、照れ隠しかな?皮肉を言ってるのかな?慣用句なのかしら?…どれもピンと来ず、どうにも気になってインターネットで調べてみたところ、北條民雄の『いのちの初夜』2の中で使われた表現だったとのこと。大林さんが辞書で遊んでてて楽しそうだから自分もやってみよーというお気楽なメンタリティに冷たい水をぶっかけられた気分になりました。『新明解』のなんという所業でしょうか。数ある本には、想像できないくらいの現実が詰まっており、辞書にはそんな現実を詰め込んだ言葉が分類されずに並んでいる(もちろん五十音順という秩序はありますが)。やっぱり面白い世界だなあと、冷たい朝の空気の中で昨夜の体験を思い出し、筆をとったという始末です。
こんなことを書いている手紙なので、「誰か」には届かなくてもいいが半分というところで。年は明けても、なかなかオトナにはなれませんね。(高)
- 金田一京助『新明解国語辞典 第四版』三省堂 1972
- 北條民雄『いのちの初夜』青空文庫(2026.1.11アクセス)
ハンセン病療養施設での出来事をテーマにした短編小説